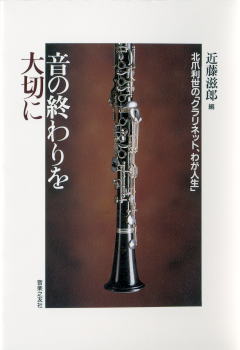昨年はR.シュトラウスの没後50年にあたり各地で記念行事が行われました。生地ミュンヒェンも、もちろん様々なイヴェントに明け暮れ、ミュンヒェン在住当会のYk支局長からは「ミュンヒェンはシュトラウス一色です!」という手紙が来たほどでした。しかしこの街はもう一人、同市縁の大作曲家のやはり没後50年を記念していたのをご存知でしょうか?
その作曲家こそがハンス・プフィッツナー(1869−1949)です。
前半は道下氏によるヴァイマール期のドイツにおける彼の活動を中心に、後半部分は高橋氏による20年代のベルリーンで爆発的に広まったジャズを中心に書かれています。
敗戦によって莫大な賠償を課せられ激しいインフレに喘ぎながらも文化的には未曾有の水準を誇った"黄金の20年代"のベルリーン。E.クライバー,B.ヴァルター,O.クレンペラーが3つの歌劇場に在り、W.フルトヴェングラーがフィルハーモニーを振っていた時代。
そんなベルリーンに在って作曲、文筆活動の他、プロイセン芸術アカデミーでH.プフィッツナーは進歩的な作曲家・ピアニストであるF.ブゾーニと共にマスタークラスで教鞭をとっていました。
この事実からも(その舌鋒鋭い言論に対する賛否はともかくとして)当時のドイツにおいていかに彼が評価されていたかをうかがうことができます。
今は忘れられているプフィッツナーについて本書は、その評価、彼の作風や事ある毎に語られたその美学が当時、時代の要請にかなっていた。或いはそれを受け入れる土壌が育まれていた。という視点からその作品を捕らえます。現在は上演されることも無いオペラ『愛の花園の薔薇』にマーラーは何故、あれほど熱中したのか。有名なカンタータ『ドイツ精神について』や氏の研究テーマであり、この作曲家の代表作である音楽的伝説『パレストリーナ』について。そしてトーマス・マンが示した彼に対する理解も同じ所にその源泉を見出すことができると。
その生涯を俯瞰する冒頭の章で個々のエピソードが布石の無いまま突然語られたり、後半クルシェーネクの『ジョニーは演奏する』に対して当時の大批評家J.コルンゴルトが展開した反対キャンペーンにふれられていない等、多少の不満はありましたが、本書にはそうした些細なことを補うだけの内容があります。
とかくR.シュトラウスによってのみ語られてきた、そして時のナチス政府との関わり故にあまり語られなかった戦間期のドイツ音楽に新たな照明をあてるこの本は今世紀初頭からの後期ロマン派と続く世代に、また文化に関心を持つ諸氏にとっては見逃せない一冊です。
プフィッツナーについては昨年刊行された以下の本もあげておきましょう。
Johann Peter Vogel "Hans Pfitzner ~Leben・
Werke・ Dokumente"
Atlantis Musikbuch-Verlag
去る4月29日フルトヴェングラー研究会管によって成された『クリスマスの妖精』※序曲の日本初演にあたり、著者の一人である道下氏にお会いする機会を得ました。
たまたま耳にしたチェロ・ソナタの美しさに、プフィッツナーを研究対象とした由。今後の活躍を期待しましょう。
※"Das Christelflein"op.20
1906/18よく『キリストになった子悪魔』と訳されているようですが同管のプログラムにあった『クリスマス〜』の方が作品にふさわしいと思いますのでこちらを使用しました。
|